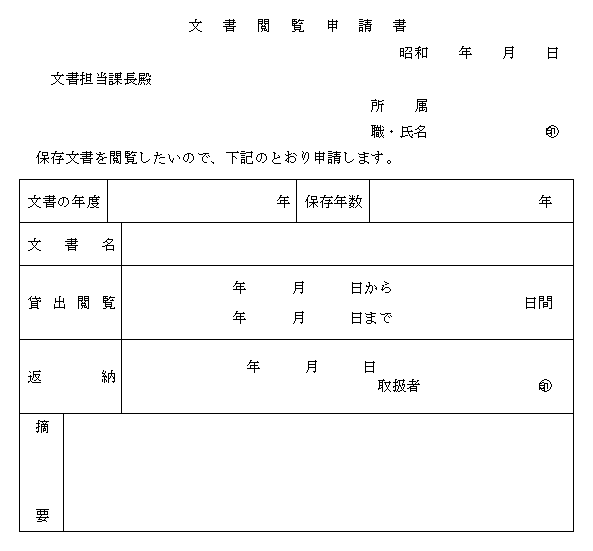○豊能町文書取扱規程
昭和57年7月20日訓令第3号
豊能町文書取扱規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される文書をいう。
(3) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置で、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行つたものの作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い常に処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
(文書担当課長の職務)
第3条 総務部総務課長(以下「文書担当課長」という。)は、町における文書事務を総括する。
(主管課長の職務)
第4条 各課・支所等(以下「主管課」という。)の長(以下「主管課長」という。)は、常に文書事務の円滑適正な取扱いに留意しなければならない。
(文書取扱責任者)
第5条 主管課に文書取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は主管課のなかから主管課長が指定する。
3 主管課長は取扱責任者を指定したときは、直ちにその職及び氏名を文書担当課長に報告しなければならない。
(取扱責任者の掌理事項)
第6条 取扱責任者は、次の各号に掲げる事項を掌理する。
(1) 主管課の文書の収受、配布及び発送の手続に関すること。
(2) 主管課の文書の審査に関すること。
(3) 主管課の文書の処理及び改善に関すること。
(4) 主管課の条例、規則及び規程に関すること。
(5) 主管課の文書の整理及び管理の指導に関すること。
(6) その他主管課の文書の取扱いに関すること。
(取扱責任者の会議)
第7条 文書担当課長は、必要があるときは、取扱責任者の会議を招集し、文書事務の連絡調整を図らなければならない。
(公示、令達文書の種類)
第8条 公示文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの
(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの
(3) 告示 法令、条例又は規則に基づいて住民に周知させるために公示するもの
(4) 公告 告示以外のもので、住民に周知させるために公示するもの
2 令達文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訓令 庁中の事務処理又は一定の事項に関する命令で、公示を要するもの
(2) 庁達 庁中の事務処理又は一定の事項に関する命令で、公示を要しないもの
(3) 内訓 特定の職員に対し、秘密に属する事項について命令するもの
(4) 達 特定の個人又は団体に対し命令するもの
(5) 指令 申請又は願出等に対して許可、認可、指示又は命令するもの
(令達番号)
第9条 公示令達文書は、文書担当課に備えた公示令達簿(様式第1号)に、公示令達の種類ごとに年間を通じて一連番号を付けるものとする。
(文書番号及び記号)
第10条 収受及び発送文書には、次の各号に掲げる番号及び記号を付けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(1) 収受文書には、主管課等に備えた受発件名簿(様式第2号)の受付番号を付けるものとする。
(2) 発送文書には、「豊能」の次に主管課等の頭文字、受発件名簿の発送番号を付けるものとする。
(3) 文書番号は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもつて終わり、主管課ごとに一連番号を付けるものとする。
第2章 収受及び配布文書事務
(文書の収受)
第11条 文書は、文書担当課において収受する。ただし、主管課において直接収受した文書は当該課において収受するものとする。
2 勤務時間外に到着した文書は、宿日直者が収受し、文書担当課に送付しなければならない。
(収受文書の分類)
第12条 前条の規定により収受した文書は、公文書と私文書に、また公文書については、次の各号に掲げる文書(以下「特殊文書」という。)、総合行政ネットワーク文書及びその他の文書(以下「普通文書」という。)に分類する。
(1) 親展文書
(2) 書留文書(現金書留を含む。)
(3) 電報
(4) 特別送達文書
(5) その他文書担当課長が特殊文書として取り扱うことが適当と認めた文書
(私文書の取扱い)
第13条 発信人が個人名で、あて名が職名のない個人名であるものを私文書とし、これ以外のものは、公文書として処理する。
2 私文書は、公文書と同様の方法により配布する。
(公文書の取扱い)
第14条 特殊文書は、文書担当課に備えた特殊文書受付簿(様式第3号)に記入した後配布して受領印を受けなければならない。
2 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、当該総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証し、発信者に対して受領又は否認をした旨の通知を送信するものとする。
3 文書担当課において受信し、受領を通知した総合行政ネットワーク文書は、主管課の取扱責任者に配信するものとする。
4 普通文書は、文書区分箱、又は主管課に配布することにより処理するものとする。
(配布文書の取扱い)
第15条 取扱責任者は、文書の配布又は配信を受けたときは、その主管範囲に属するものであることを確認し、総合行政ネットワーク文書にあつては、紙に出力し、事務担当者に配布するものとする。
2 事務担当者は、文書の配布を受けたときは、公文書については、受付印(様式第4号)を押した後、受発件名簿に記入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる処理経過を要しない配布文書は、記入を省略することができる。
(1) 単なる通知書、諸届、案内状、定期報告書、見積書、請求書、領収書、その他これに類するもの
(2) 新聞、パンフレットその他これに類する印刷物
(3) その他軽易な文書
(配布文書の供覧)
第16条 事務担当者は、受付手続が終わつた文書の上部余白に供覧印(様式第5号)を押して主管課長に供覧しなければならない。
2 主管課長は、供覧文書の処理について上司の指示を受ける必要があると認められるものは、速やかに上司に供覧し、その指示を受けなければならない。
第3章 処理文書事務
(事案の処理)
(1) 帳票処理 (成規の様式等による帳票に処理案を記載すること。)
(2) 余白処理 (軽易定例な文書でその余白に処理案を記載すること。)
(3) 経由処理 (経由文書で副申又は通知を要しない文書を処理すること。)
(起案文書の作成等)
第18条 起案文書は、次の各号に定める要領で作成しなければならない。
(1) 公用文の形式は、毛筆による文書、書簡文書、あいさつ文書等を除き、原則として左横書きとすること。
(2) 文体は、原則として、公示文書及び令達文書については「である」体、その他の文書については「ます」体を基調とする口語文とし、かなづかいは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)によること。
(3) 標題を付け、起案の理由、説明、経過及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書、参考資料を添付すること。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(4) 同一事案で決裁を重ねるものは、その事案が完結するもので関係決裁文書及び供覧文書を添付すること。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(5) 経費を伴う事案には、その旨を記載し、予算との関係を明らかにすること。
(6) 加除訂正したときは、その箇所に認印を押すこと。
(7) 合議を要するものについては、その関係部課名を記入すること。
(起案書の審査)
第19条 審査を要する文書については、取扱責任者が審査し、適当と認めるときは、起案用紙の所定欄に押印しなければならない。
(文書の合議)
第20条 他の課に関係がある起案文書は、その関係課と合議しなければならない。
2 合議を受けた課は、合議文書を速やかに、査閲し、同意、不同意を決定しなければならない。
3 合議を受けた課に異議があるときは、意見を付して上司の指示を受けなければならない。
4 合議の終わつた後、原案を改廃するときは、関係課と再度合議しなければならない。
(公文例)
第21条 公示及び令達文書並びに一般文書の公文例は別表第2に掲げるとおりとする。
(議案の取扱)
第22条 議会の議決若しくは同意を要し、又は報告等に係る文書は、文書担当課長に送付しなければならない。
第4章 浄書及び施行文書事務
(文書の浄書)
第23条 決裁済文書の浄書は、その浄書が特に複雑困難なものを除き、原則として主管課において行うものとする。
(発信者名)
第24条 発信文書は、町長名をもつて発信しなければならない。ただし、その内容が軽易な内容のものにあつては、副町長、部長、課長等名を用いることができる。
(公印)
第25条 発送文書は、原則として公印を押さなければならない。ただし、対外文書で軽易なもの及び庁内文書については、これを省略することができる。
(電子署名)
第25条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
2 電子署名を行うために必要な手続きその他の事項は、別に定める。
第5章 保管、保存及び廃棄文書事務
(文書の整理)
第26条 事務担当者は、常に文書を一定の場所に整理、保管し、その所在を明らかにしておかなければならない。
(完結文書の編集)
第27条 完結文書は、次の各号により編集しなければならない。
(1) 簿冊の編集は、文書の処理の年度ごとに、種類及び保存期間の種類ごとに行うこと。
(2) 年度を越えて処理した文書は、その文書が完結した年度の簿冊に編集すること。
(3) 同一事案で種類を異にする関連文書は、その関係の深い簿冊に編集すること。
(保存期間の分類基準)
第28条 文書の保存期間の種別は、永年、10年、5年、3年及び1年とし、その分類基準は、別表第1による。ただし、法令に定めがあるものについては、当該法定期間による。
(保存期間の起算日)
第29条 文書の保存期間は、文書の完結した日の属する年の翌年1月1日(会計年度によるものは翌年度4月1日)から起算する。
(文書の保存)
第30条 文書の保存は、主管課において保存するものとする。ただし、別表第1中、第1種(永久保存)及び第2種(10年保存)の文書については、文書担当課に引継ぐことができる。
(文書の引継ぎ)
第30条の2 取扱責任者は前条による引継ぎを受けようとするときは、文書を文書保存箱(様式第8号)に保存種別ごとに分類し、その表面に収容文書名、保存期間、主管課名、廃棄年月日を記載しなければならない。
2 取扱責任者は、分類が終了した文書について、保存文書引継書(様式第7号)を2通作成し、文書担当課に申し出るものとする。
3 引継ぎは、文書担当課の指定した日に行なうものとする。
(引継文書の審査)
第31条 文書担当課長は、前条第1項の引継ぎの申出を受けたときは、編集及び種別の適否について審査しなければならない。
2 文書担当課長は、審査の結果、不適当なものがあるときは、取扱責任者に対しその修正を求めることができる。
(保存文書の閲覧)
第32条 職員は、第30条の2により引継した保存文書の閲覧をしようとするときは、閲覧申請書(様式第9号)を、文書担当課長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 職員以外のものには、保存文書の閲覧は認めない。ただし、文書担当課長の承認を得たときは、この限りでない。
(禁止事項)
第33条 保存文書は、所定の場所以外へ持出し、抜取り、取替え、若しくは訂正又は転貸してはならない。
(保存文書の廃棄)
第34条 文書の保存年限が終了したときは、文書担当課に引継いだものは文書担当課長において、その他のものにあつては、主管課長において廃棄するものとする。
2 保存期間が満了しない文書であつても、文書担当課長又は主管課長において保存の必要がないと認めたものは、文書担当課に引継いだものにあつては主管課長に合議したうえ文書担当課長において、その他のものにあつては主管課長において廃棄することができる。
3 保存期間が満了した文書であつても、文書担当課長及び主管課長において保存の必要があると認めたものは、更に期間を延長させることができる。
(廃棄文書の処置)
第35条 廃棄文書で、他に利用されるおそれがあるものは、寸断し、又は焼却する等適切な処置を行わなければならない。
第6章 雑則
(細則)
第36条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 豊能町文書取扱規程(昭和41年豊能町規程第1号)は廃止する。
3 豊能町文書保存種別の標準規程(昭和40年豊能町規程第5号)は廃止する。
附 則(昭和61年2月5日訓令第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日訓令第1号)
この規程は、昭和62年6月1日より施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月1日訓令第6号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成15年8月22日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月29日訓令第7号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日訓令第1号)
この規程は、平成22年12月28日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
第1種(永年保存)
(1) 町議会の議決書及び議事録
(2) 条例、規則、告示、訓令、訓達及び指令の原議及び関係書類
(3) 町広報
(4) 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類
(5) 退職年金及び遺族年金に関する文書
(6) 褒賞に関する文書
(7) 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書
(8) 調査及び統計で特に重要な文書
(9) 事務引継ぎに関する重要な文書
(10) 財産及び町債に関する文書
(11) 工事関係書類で特に重要なもの
(12) 認可、許可又は契約に関する特に重要なもの
(13) 町の分合、境界変更及び名称の変更その他町の沿革に関する文書
(14) 予算、決算及び出納に関する重要なもの
(15) その他永年保存の必要を認められるもの
第2種(10年保存)
(1) 府の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書
(2) 認可、許可又は契約に関する軽易なもの
(3) 原簿及び台帳
(4) 予算、決算及び出納に関する帳票及び証
(5) その他10年保存の必要を認められるもの
第3種(5年保存)
(1) 租税その他各種公課に関するもの
(2) 補助金に関する書類
(3) 調査、統計、報告、証明等に関するもの
(4) 物品に関する重要な書類
(5) その他5年保存の必要を認められるもの
第4種(3年保存)
(1) 当直日誌、出勤簿、出張命令簿等職員の勤務の実態を証するもの
(2) 照会、回答その他往復文書に関するもの
(3) その他保存の必要を認められるもの
第5種(1年保存)
(1) 文書の収受、発送及び処理に関するもの
(2) 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの
(3) 軽易な照会、回答その他の文書
(4) その他軽易なもので1年保存の必要を認められるもの
別表第2(第24条関係)
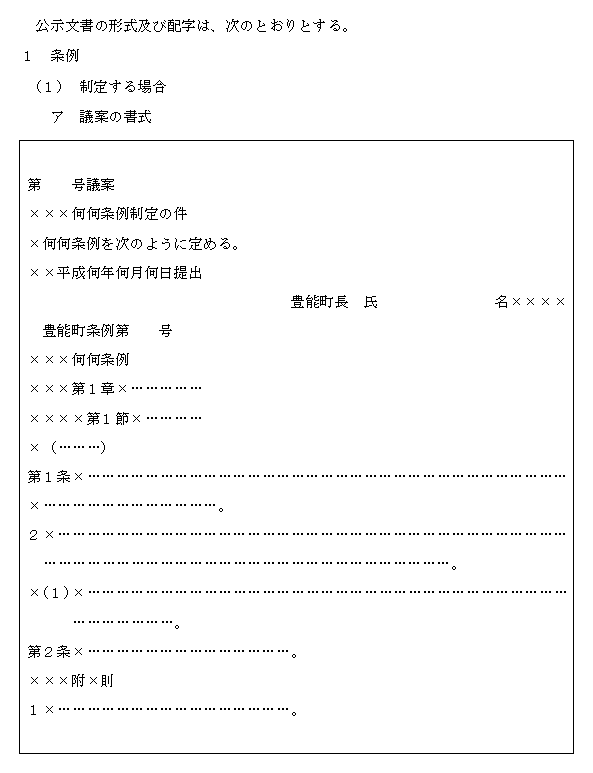
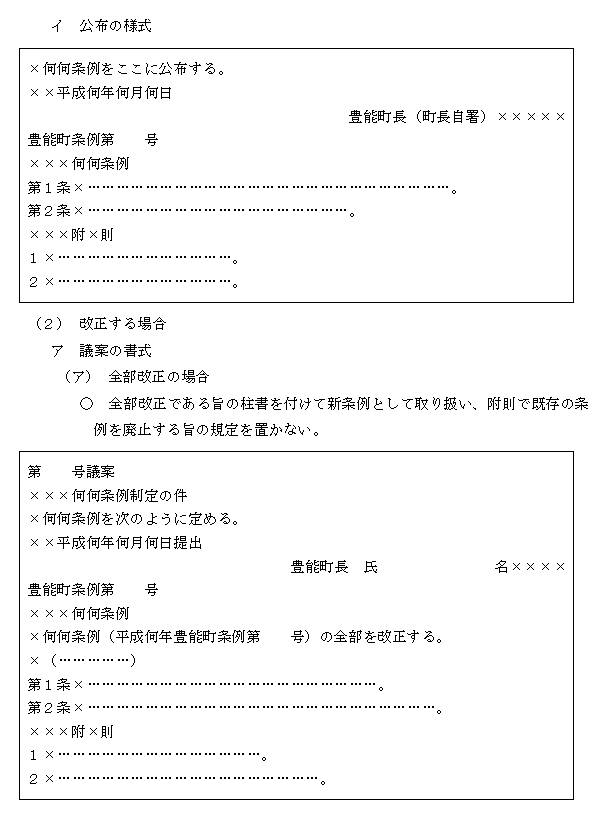
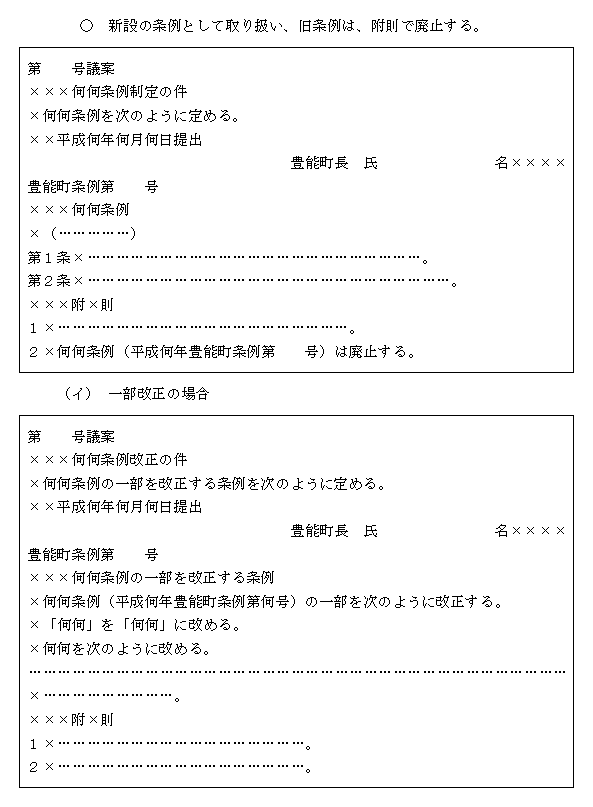
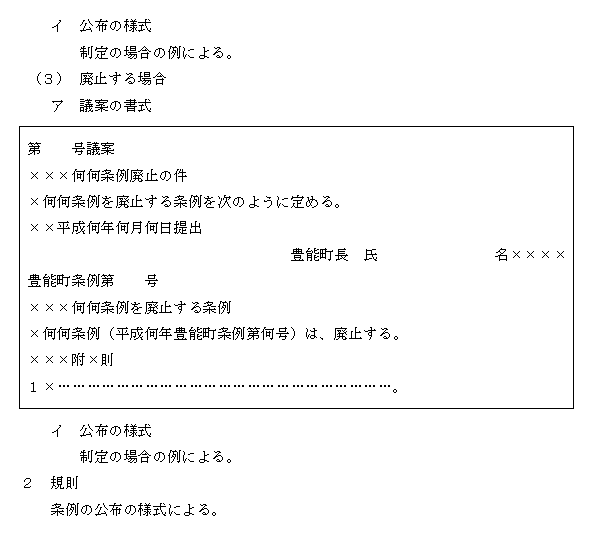
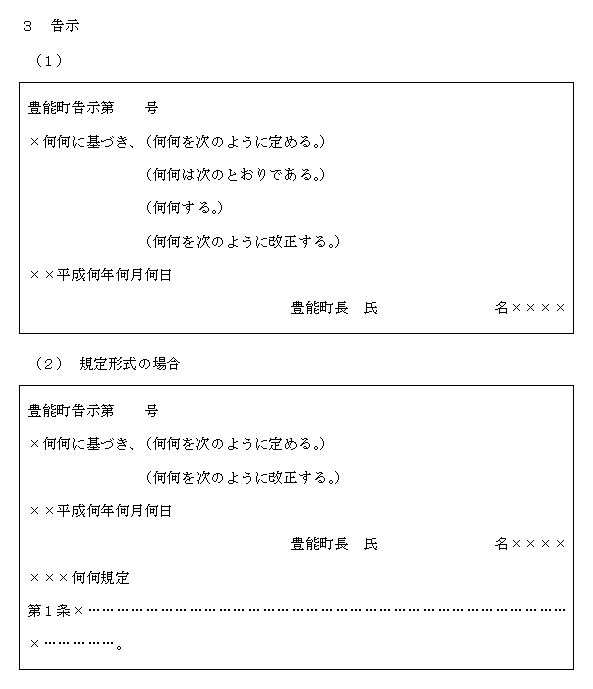
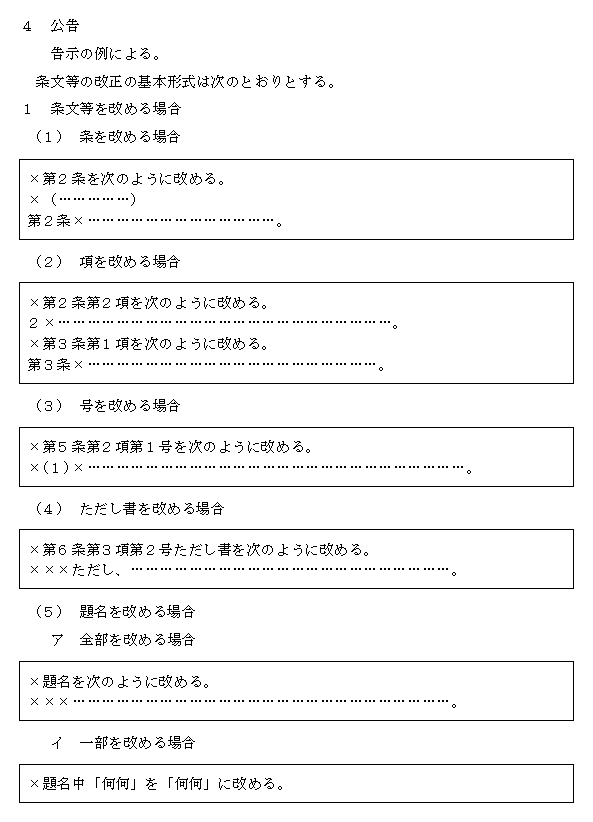
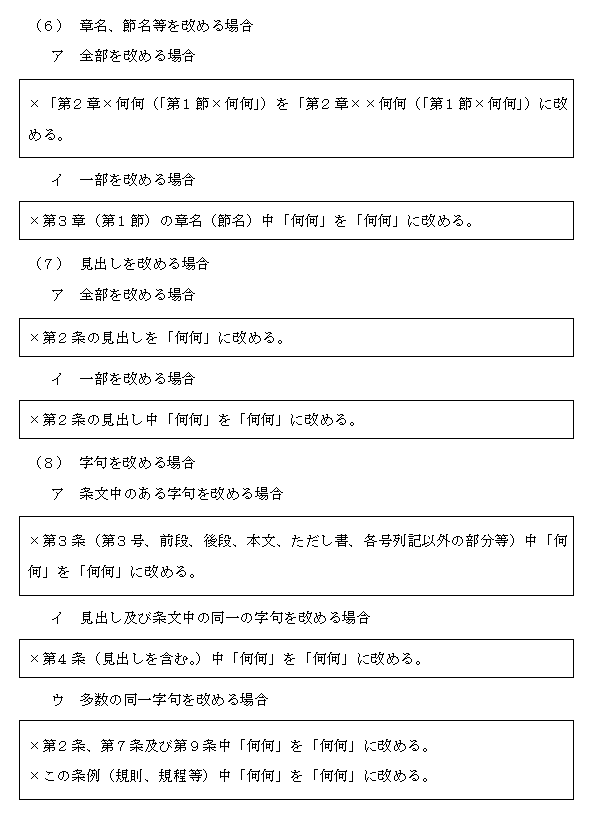
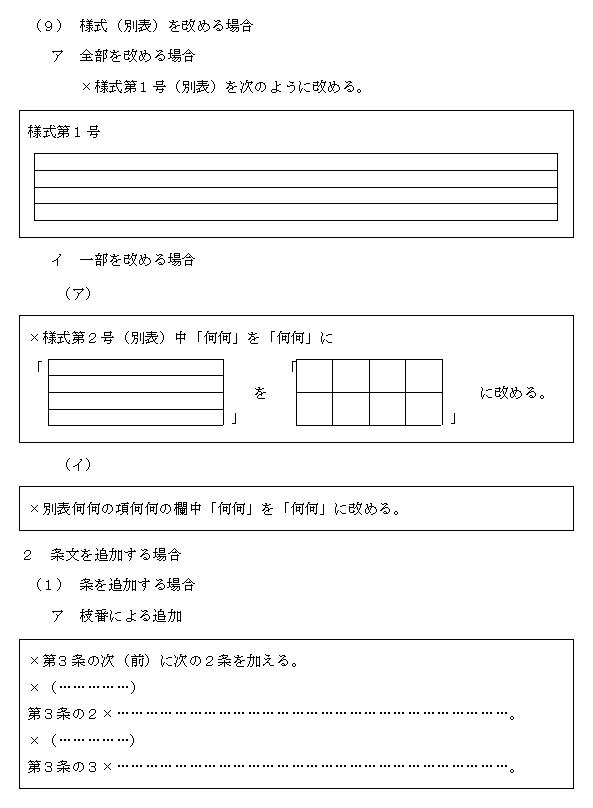
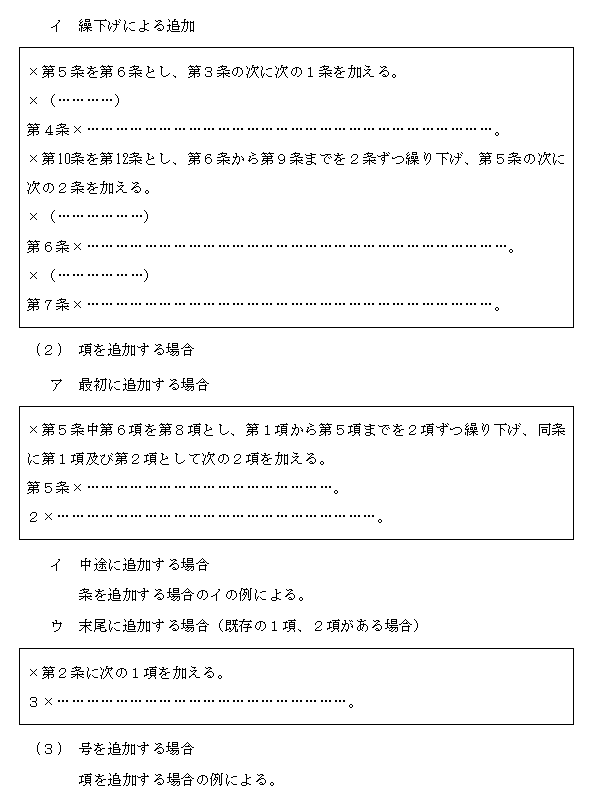
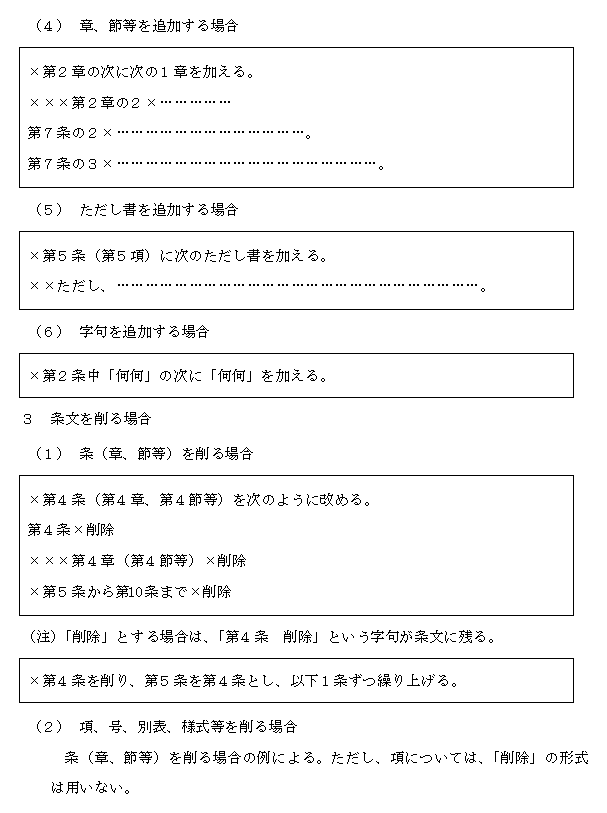
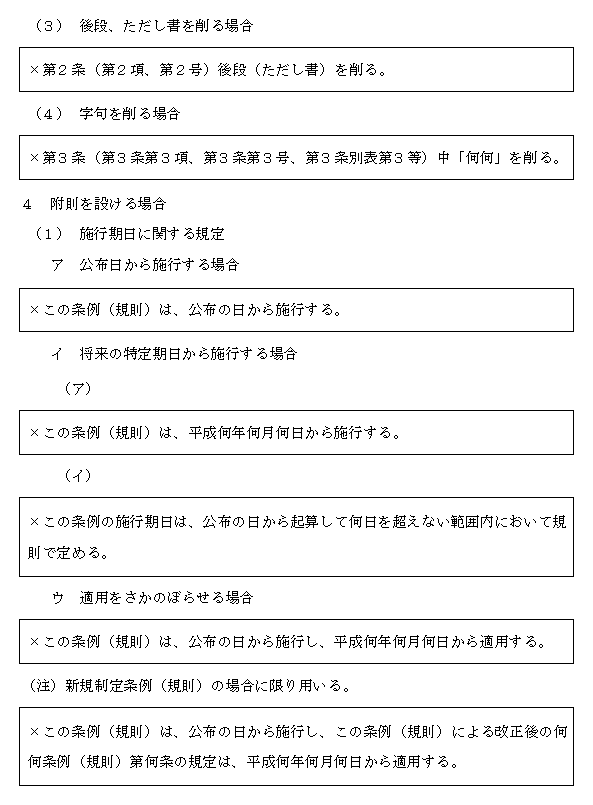
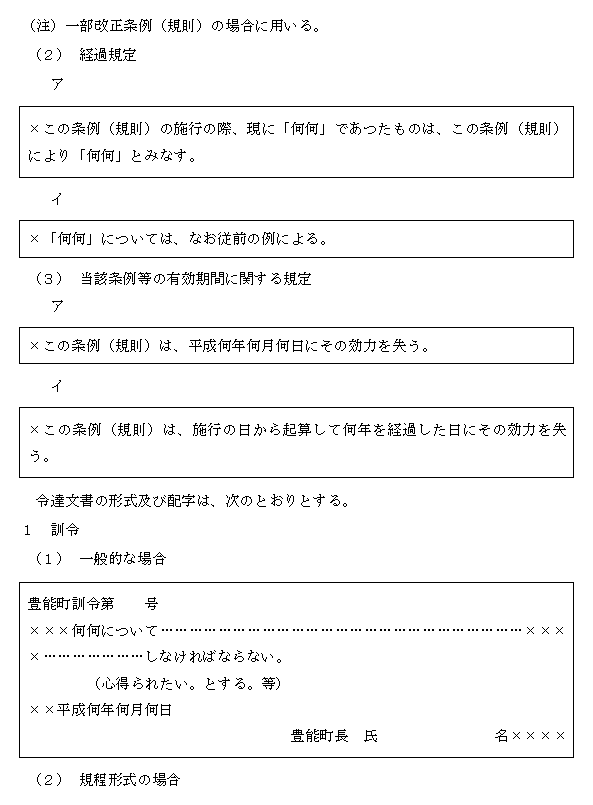
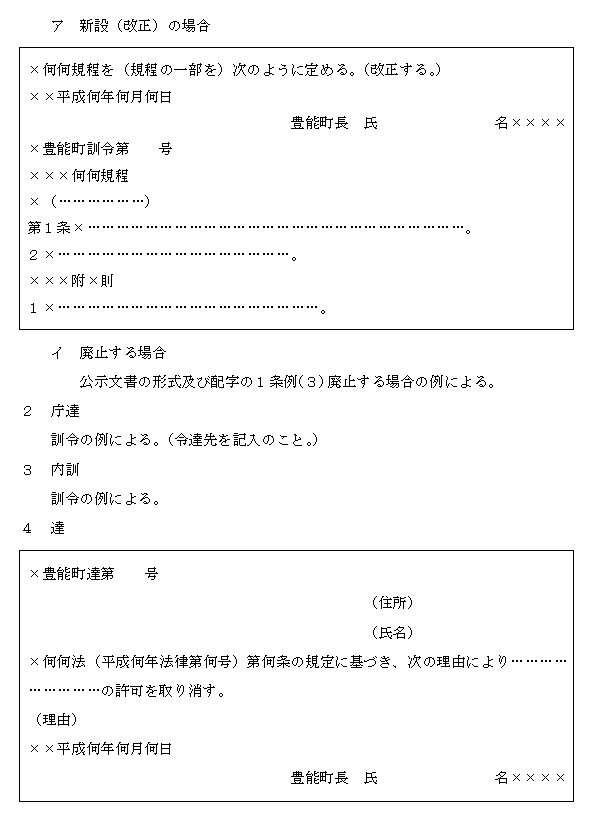
様式第1号(第9条関係)
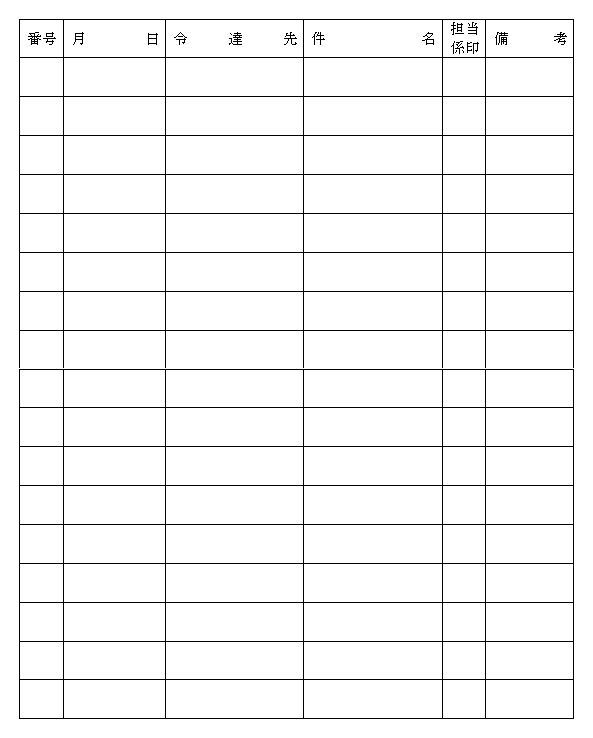
様式第2号(第10条関係)
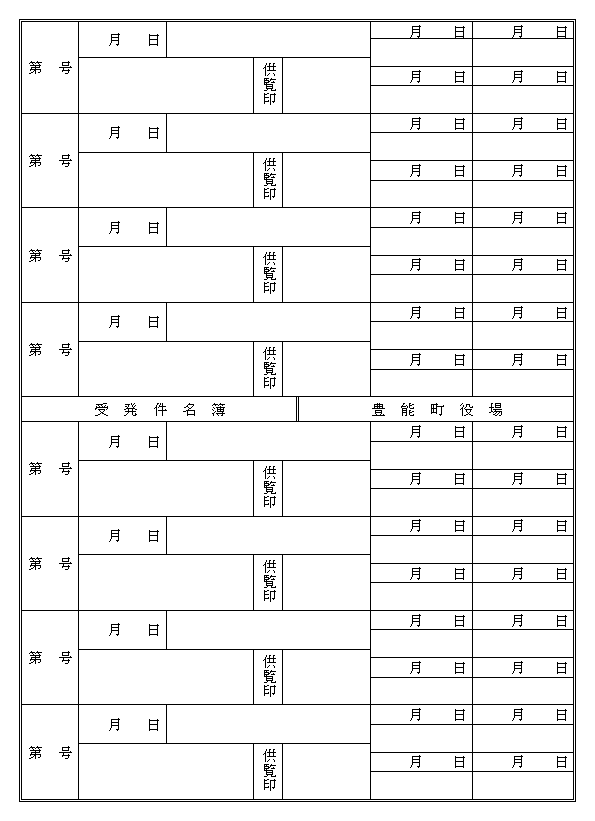
様式第3号(第14条関係)
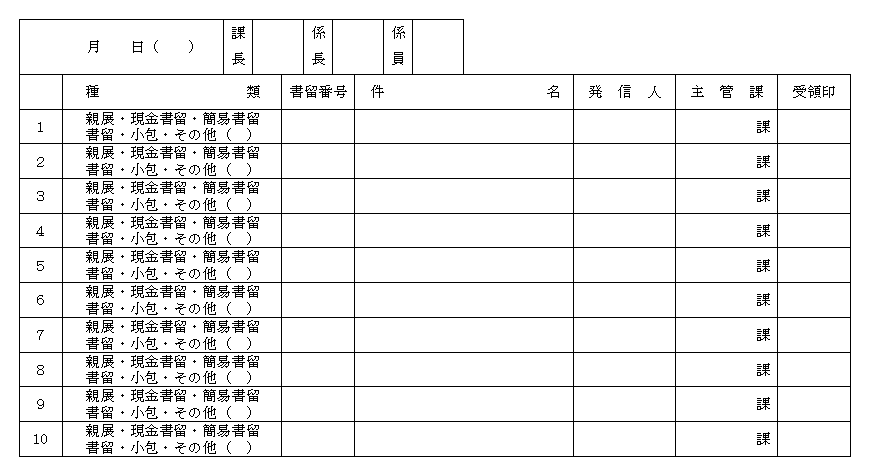
様式第4号(第15条関係)
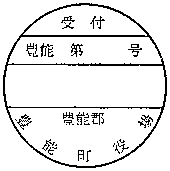
様式第5号(第16条関係)
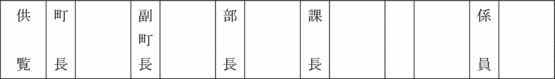
様式第5号の1(第17条関係)
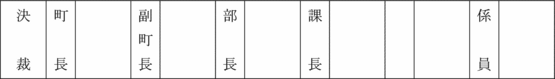
様式第6号(第17条関係)
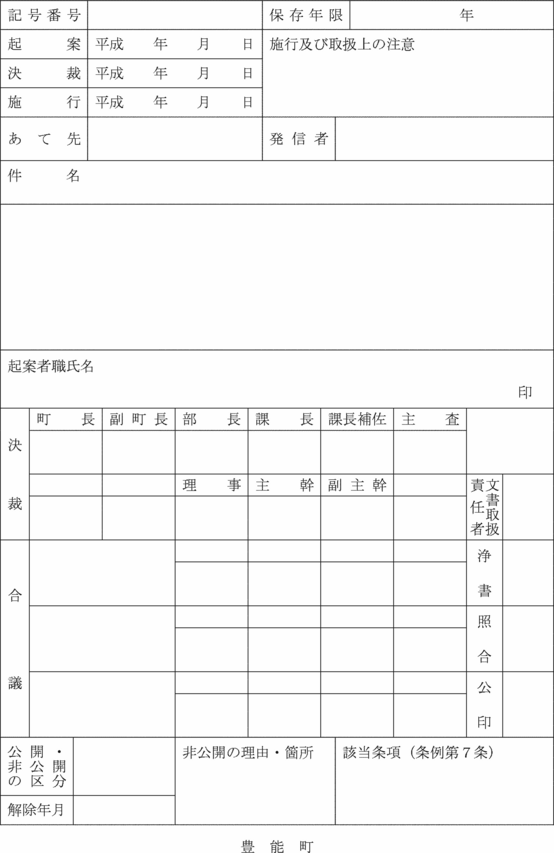
様式第7号(第30条関係)
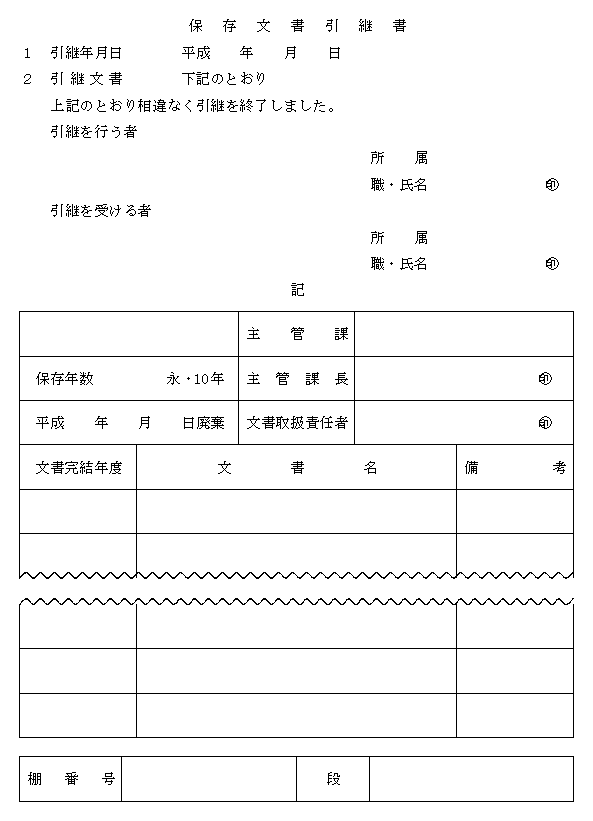
様式第8号(第30条の2関係)
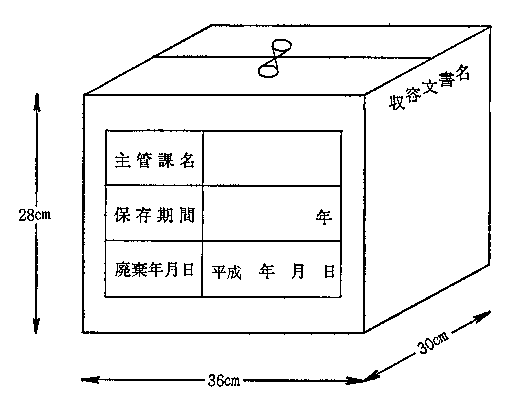
様式第9号(第32条関係)